「気持ちは分かるけど、あまり感情的にならない様にね。」
「落ち込んでもしょうがないし、次行こう次!」
こんなセリフを部下に投げかけた記憶はきっと皆さんにもあるはずだ。
一見とても理性的で部下を気に掛けた模範的な回答に見える。
厳しい指導が難しいご時世で部下を励ますために出た「100%前向きなの言葉」かも知れない。
この思わずついて出てしまう言葉。
部下にとっては厳しい指導や叱責以上に強烈な「暴力」かも知れない。
マイナス感情の否定は危険
もう一度整理をしたい。
「感情的にならない様に」
「落ち込まない様に」
前後に優しい装飾をつけたとしても、これは明確な「感情の否定」に他ならない。
言われた部下もきっと「そうだよな」と思って頷くかもしれない。
「励まされた」とやる気を持ち返すかも知れない。
でもその「正しさ」が繰り返されていくと、少しずつ感情の居場所はどんどん失われていく。
怒ったり、落ち込んだり、泣いたり…
そんな自然に沸き立ってしまうマイナスな感情を「間違い」とされてしまうと
彼らは次第に「感情を感じること」すら躊躇うようになる。
そして、そこに残るのは「正しさ」だけだ。
人を動かすのも、組織を動かすのも「正しさ」だけじゃない。
怒りが行動を生むこともある。悔しさが変化を作ることもある。
部下の感情に蓋をすることで、行動の種まで摘み取ってしまっていないか。
「落ち込んでもしょうがない」は、もしかしたら、
「俺の感情以外は職場にとって邪魔なんだよ。」
と、ほぼ同義かもしれないのだ。
プラス感情の肯定はもっと危険
もっと危険なのは「プラスの感情だけを肯定する組織」になってしまうことだ。
やる気のある部下、モチベーション高く成果を上げてくれる部下。
何もしなくても勝手に動いて勝手に成果を上げてきてくれる。
上司にとってこれほどありがたいものはない。
頑張っているとき、成長しているとき、成功しているとき。
そんな時にポジティブな感情を認め、喜び、称賛する。
これの何が危険なのか、と思う方もいるかも知れない。
褒めて伸ばすのはマネジメントの基本であると、どんな研修でも教えられる事だ。
しかしよく考えて欲しい。
この一連の流れは
「マイナスな感情は否定されるべき悪で、プラスの感情だけがその存在を許されている」
状況だ。
そんな組織ではやがて部下たちは「感じる」こと自体にフィルターをかけるようになる。
◾️うれしい気持ちしか口にできない。
◾️苦しい気持ちは言えない。
◾️落ち込んでいる自分はダメだと自己否定する。
こうして職場が「理想的な感情」を演じる場所に変わっていく。
表向きは明るく前向きに見えるかもしれない。
しかしその実態は、勝手に成果を上げるエースだけが活き活きし、
我々がもっとも力を入れるべき中間層の存在が否定され居場所を失ってしまう世界。
感情の自由を奪われた、静かなディストピアだ。
【自己決定理論(Self-Determination Theory)】
この問題を理解するために、自己決定理論(Self-Determination Theory/SDT)という心理学の考え方に触れておきたい。自己決定理論はエドワード・L・デシ(Edward L. Deci) と リチャード・M・ライアン(Richard M. Ryan)によって1985年にその体系がまとめられており、人が自ら動き続けるためには、3つの基本的な心理欲求が満たされる必要があるとする理論だ。
- 自律性(Autonomy)
── 自分の意志で選び、感じ、行動しているという感覚 - 有能感(Competence)
── 自分にはできる、成長しているという実感 - 関係性(Relatedness)
── 自分は誰かと繋がっているという安心感
この3つのうち、今ここで最も重要なのが「自律性」だ。
人は自分で感じ、自分で考え、自分で動けるとき、はじめて本当の意味でエネルギーを発揮する。
逆に言えば「こう感じるべき」「こう思うべき」「こう振る舞うべき」と、感情や行動を他者にコントロールされ続けると、自分で動こうとする意欲は静かに、しかし確実に失われていく。
「落ち込むな」
「感情的になるな」
一見励ましに見えるこれらの言葉も突き詰めれば、
部下の内側から自然に湧き上がった感情に対して「違う」と言っている
ことになる。
これを繰り返すと、部下は徐々に
「自分で感じてはいけない」
「正しい感情を持たなければならない」
という無意識のプレッシャーに晒されるようになる。
こうして部下が自らの感情を放棄せざるを得なくなり他人基準になったとき、行動もまた他人基準になる。
結果としてモチベーションは「自分のため」ではなく「誰かに認められるため」だけのものになり、やがて行動エネルギーは細く弱くなっていく。
感情はそこにあるもの。他人が触る事は許されない。
では、どうすれば部下たちの感情の自由を守り、
行動のエネルギーへと育つ環境を作ることができるのか。
ここでは、3つの実践アプローチを紹介したい。
◾️「感情を止めない」
どんな感情が出てきても、それを止めようとせず「それは良い」「それは悪い」とジャッジしない。
怒りでも、悔しさでも、悲しみでも、ただそのまま受け止める。
「そっか、そう感じたんだな。」
「それはつらかったな。」
「怒るのも無理ないよな。」
そんなふうに感情を一度、素通りさせることに徹する。
それだけで部下の「自分で感じる力」は守られる。
自己決定理論でいう自律性を根本から支えるアプローチだ。
◾️「感情を行動に翻訳する」
感情を無理にポジティブにもネガティブにも変換しない。
ただその感情を「次に何をするか」に繋げるサポートをする。
「この悔しさを次にどう活かすか一緒に考えようか。」
「聞いてるだけで俺もムカついてきたわ。客なんて勝手なんだから
逆手に取って先回り対策できそうじゃない?」
怒りや悲しみ、悪感情それ自体が悪いわけではない。
そしてそれらを止める必要も止める術も我々は持ち合わせていない。
溢れ出させるだけは勿体無いので、だったら言語と行動に翻訳して有効活用すれば良い。
行動に変わるきっかけを、部下と一緒に探すことが大切だ。
◾️感情を自分のものとして返す
上司が「理解した」「共感した」と踏み込んでしまうと、
いつのまにか部下の感情は上司に管理されるものになってしまう。
感情はその人の心から勝手に湧いて出てくるもの、これではただの泥棒だ。
これまでの実践で部下のもやもやした感情を一緒に言語化・行動化が出来ている。
「その気持ちはお前だけのもので、ちゃんと大事にしなきゃいけない。」
メッセージを添えて返してあげれば良い。
それを「君自身が持っていていい」と認める。
これが部下の感情の自律性を最高に尊重するあり方だ。
この3つの積み重ねが「自由な感情」から行動が生まれる組織を育てていく。
それが、誰かを本当に信じるということだ。


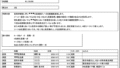
コメント