「日報って意味あるんすかね?」
そう漏らしたのは、飲み会の席での他店の若手営業。
わざわざ飲みにきてまで若手にこんな話を振られる自身の不甲斐なさに苦笑しつつ、彼の話を聞いてみる。
日報を書く暇もないほど業務に追われている。
支店や本社からは日報をデイリーに書く様に定期的な指導が入る。
そろそろヤバいなと思って書いても所長は忘れた頃に承認してくる。
ようやくの承認を確認したらコメント無し承認か「⚫︎⚫︎の件、進めておいてください」
進めるどころかもう終わってるっつーの…
本社からは効果測定のためと言われたがそのフィードバックは無し。
「書く」のは労力だ
日報を書くという行為は、単なる報告ではない。
その日どんな行動をしたか、その時何を感じたか、次にどう活かすか。
この3つを整理するだけでも頭に「いらない」リソースが割かれる。
もっと言うとストックしておきたい件は「うまく隠さなきゃ」いけない。
日報を書く側はエネルギーを使っている。
その労力は言い換えれば「信頼の前借り」だ。 自分の時間と考えを誰かに預ける行為。
それに何のレスポンスもないなら書く意味がないと思うのは、自然な反応だ。
「承認ボタン」は「承認していない」のと同じ
日報を承認するという行為。
承認ボタンひとで済む手続きかもしれない、それでも溜めるマネージャーがいる。
前項の通り『日報を書く』と言う行為は部下にとって一見何の生産性もない行為だ。
時間を取られる上になんの生産性もない、評価にも繋がらない。
(日報を頑張って書いているから評価はB!という会社があれば教えて欲しい。)
つまり部下にとって日報は「自分のためにならない仕事」なのだ。
もっと分かりやすく言うと「上司を助けてあげるための仕事」である。
そんな苦行を1秒も掛からない承認ボタンだけで処理されたら部下はどう思うか。
「こいつ、俺が自分のためにならない日報をうるさく言うから、実務時間を割いてまでお前のために書いてやってんのに、お前はふーん、と眺めてボタンひとつで済ましてんのかよ。しかも1週間も経ってから。お前が『進めてください』とかコメントした案件、進むどころかもう終わってるっつーの。てかお前は??お前書いてなくね?『プレイングマネージャー』だから俺らよりずっと訪問少ないじゃん?2-3件しか回ってないやつに日報書いてないって言われても知らんがな。そもそもお前がまずかけよ。」
日報が形式化する瞬間である。
そもそも日報は、上司が部下の行動や思考を把握し、育成や支援につなげるためのツールだったはずだ。
それがいつの間にか
『部下が1日の業務を丁寧に整理して上司に提出し、上司が管理しやすいように整えてあげる仕事』
になっている。
完全に逆だ。
しかもその対価が「無反応」だったり、「承認ボタン(私は承認とは認めない)」
だったりするから部下からすればたまったもんじゃない。
上司の仕事は、部下に日報を書かせることではない。
日報に散りばめられた言葉を、その言葉に込められた温度を丁寧に翻訳しそれを受け止めることだ。
その順序が逆転している事を理解出来なければ、部下の心は成層圏を飛び越えて帰ってこなくなる。
上司にとっての日報の意味
部下の日報は単なる報告ではない。 それは“部下の頭の中”をのぞく唯一の機会だ。
どんなことに悩んでいて、 何に気づいていて、 どこで止まっているか。
行動の記録ではなく思考の記録だ。
とはいえ部下の日報におけるモチベーションは最低だ。
そのため一見ただの「業務報告」になってしまう。
それでも上司はその業務報告にこめられた「意図」をきちんと読み解かなければならない。
「結果だけ見ればいい」と承認ボタンで終わらせる上司は、 部下の変化に気づけず育成のタイミングも逃す。
日報とは「部下が自分の言葉で自分を整理するプロセス」であり、
上司が「その思考に寄り添い、方向づけをするチャンス」でもある。
部下は言語化がめちゃくちゃ苦手だしモチベーションは限りなく低い。
それでも上司はそれをしっかりと読み解かなければならない。
心理的安全性とエンゲージメント
ここで一つ理論の話をしておきたい。
◾️心理的安全性(Psychological Safety)
組織論の研究者、エイミー・エドモンドソン(Amy Edmondson)が提唱した概念。
「この職場では、対人関係上のリスクを取っても安全だ」とメンバーが感じられる状態を指す。
心理的安全性は「Googleが広めた概念」と思われがちだが、そのルーツはずっと深い。
2015年、Googleが成功するチームの条件として「心理的安全性(Psychological Safety)」を挙げたことが注目を集めた。
そしてその理論自体は、1999年にハーバード大のエイミー・C・エドモンドソン教授が提唱している。
だがさらに遡れば、カール・ロジャースという心理学者がすでに同じ本質にたどり着いていた。
彼は1950年代から「人は、安心できる関係の中でこそ成長する」と説き、
これを「受容」「共感」「自己一致」の3つの柱で支えていた。
言葉は違えど「否定されない環境が、人を強くする」という構造は同じだ。
心理的安全性は、時代を超えて何度も再発見される“人間理解のコア”なのかもしれない。
コメントは指導ではなく「信頼契約の履行」
上司として日報にコメントを返すことは「指示する」という上からの行為であってはならない。
部下が差し出した「思考と感情」に対して「アンサー」で返す信頼関係の構築だ。
だからこそ、内容が稚拙でも結論がズレていても、ぶっきらぼうで不満足な内容だったとしても、
返す側は「反応すること」に意味がある。
それを無視すれば「もうこの人に報告する意味がない」と部下は思ってしまう。
そうなってしまった時点で 日報は部下にとって「千日戒行」に匹敵する苦行になるのだ。
とにかく褒めろ。承認欲求を満たして満たして「満たしまくれ」
じゃあ一体日報には何をコメントすればいいのか。
答えはこの2つだけだ。
◾️『指導をするな』
さっき言った通り、部下にとって日報は千日戒行にも劣らない苦行だと言う事を念押ししておく。
そんな中やっとで書いてやった日報に対して上司からこんななこと言われたらどう思うか胸に手を当てて考えてほしい。
「この案件はもっと前倒しできたはずです。」
「訪問件数が足りていないです、2割増を目標にして下さい。」
「失注の原因を深掘りして別途報告して下さい。」
こんなコメントが忘れた頃にやってくる、厄災以外のなにものでもない。
教会の懺悔室に通う人間だって赦しを求めてやって来る。
望んでもいないのに赦しどころか厄災を降らしてくる、そりゃ書かなくなる。
少しだけ真面目な話をすると『日報は誰でも見ることが出来る』事を忘れてはいけない。
多分このブログを見ている皆さんの会社でも日報はシステム化されており、
社内の『大多数の人間が閲覧できる状況』であると思う。
日報での指導はどれだけ正論であったとしても、受け取る部下にとっては、
『公開処刑のパワーハラスメント』と同じだと言うことを忘れてはいけない。
◾️『とにかく褒めろ』
じゃあ、どうすればいいのか。
とにかく褒めて褒めて褒めて、承認欲求を満たして満たして、満たしまくれば良い。
もし褒めるところがなかったら、共感すればいい。
どうしても指導したければ言葉を変えて伝えればいい。
「このタイミングでのクロージング、さすがですね。」(褒め)
「案件が増えると、思った様に回れなくなりますよね、俺も葛藤でした」(共感)
「なんかいつもの⚫︎⚫︎さんらしさがないね。最近負荷ちょっと高かったよね」(言い換え)
もう一度問います。あなたは日報を読んでいますか。
いま言った事は我々がプレイヤーだった頃にずっと言語化出来ていなかった思いだ。
それを我々はいつも間にか忘れてしまっている。
時代が変わっても、部下だってきっと同じ悩みや期待、怒りや不安を抱えているはずだ。
だからこそ問いたい。
『あなたは日報をちゃんと読んでいますか。』
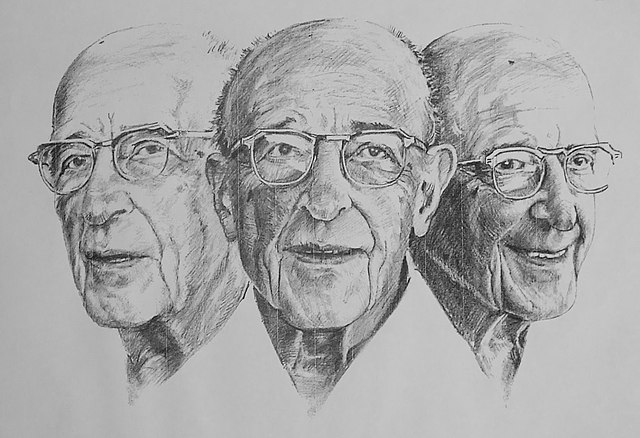


コメント